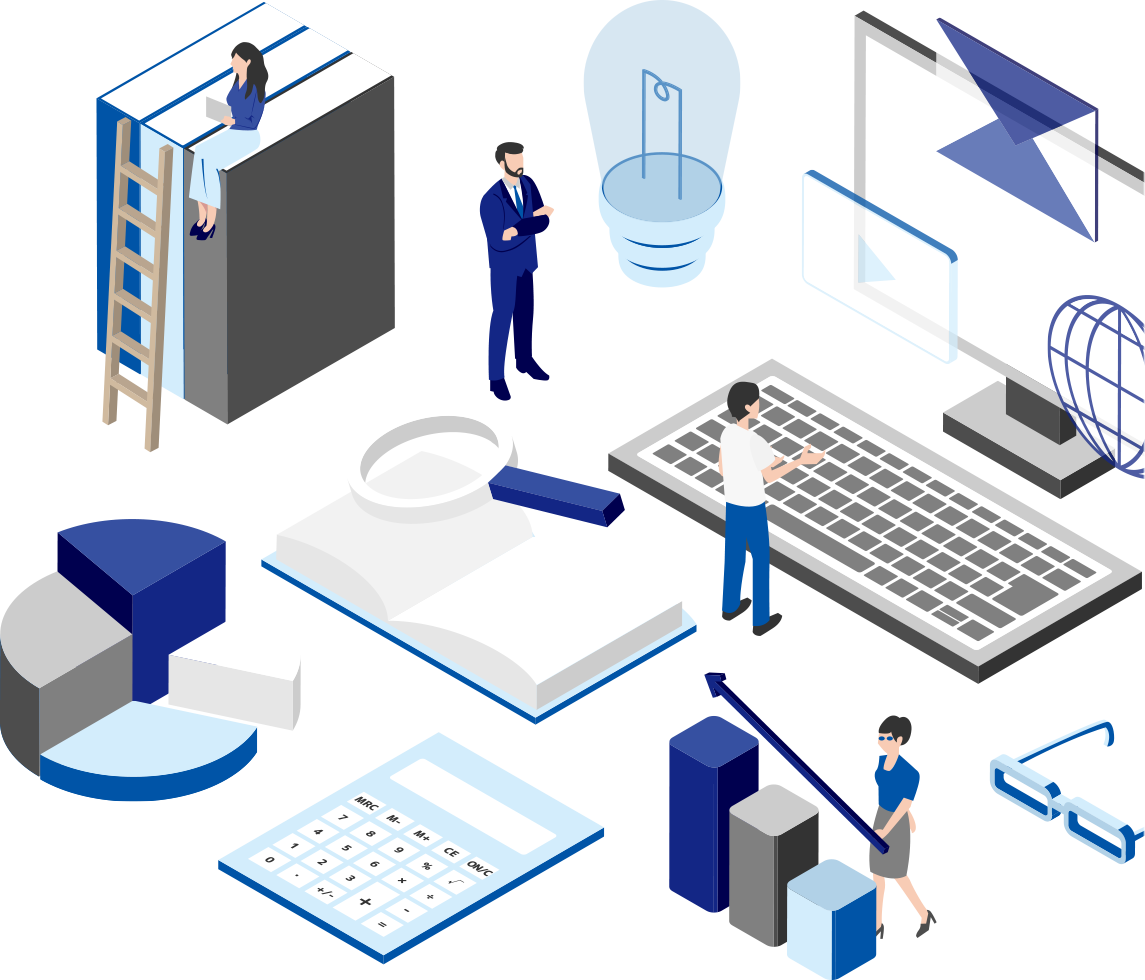DIG社会保険労務士法人の社労士ブログ
こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。
今回は、「年間の勤務カレンダー」についてお話します。
今回のブログでは、変形労働時間制やフレックスタイム制を取る場合は除外してご説明しております。ご了承ください。
皆様の会社では「年間の勤務カレンダー」というものはございますか?
年間の勤務カレンダーとは「1年間の労働日・公休日」を定めるもので、1年の始まりである1月1日起算とする会社が多いです。
起算日に決まりはありませんので、会社毎に決めることができます。
年度始まりの4月1日にする会社もありますし、36協定の起算日に合わせるという会社もあります。
「私の会社は土日祝日休みで一般的なカレンダーどおりだから不要だよね!」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
仮に営業日が一般的なカレンダーどおりの企業であっても、年間の労働日数の管理のために「年間の勤務カレンダー」を作成することをおすすめします。
そもそも「年間の勤務カレンダーは何のために作成するのか」について、次にお話します。
年間の勤務カレンダーはどうして必要?
そもそも年間の勤務カレンダーを作成する目的は「年間の労働日数・労働時間」を把握するためです。
年間の労働日数や労働時間が必要になるシーンには、以下のようなものがあります。
①残業代計算をする際の1時間あたりの単価を計算するとき
②欠勤や休職した社員の給与を日割計算するとき
③求人広告等に記載するとき
例えば①の残業代計算を見てみましょう!
月給者の残業代は、以下のようにして計算をします。
月給者の残業代=(基本給+諸手当)÷月の平均所定労働時間×残業時間
※残業計算に含めないことができる手当もあります。
※「月の平均所定労働時間」を使わないケースもあります。
月の平均労働時間は、年間の労働時間を12か月で除したものです。
年間の労働時間は、年間の労働日数×1日の所定労働時間で計算しますので、年間の労働日数が決まっていないと残業代が正しく計算できないのです。
そのために必要なのが「年間の勤務カレンダー」ということになります。
年間の勤務カレンダーを作成しないとどうなる?
今回のブログを読んでいただいて、こう思われた方もいるかもしれません。
…「年間の労働日数って毎年変わるから、残業代計算で使用する「月の平均労働時間」も毎年変わるってこと?」
はい。そのとおりです。毎年変わります!
給与計算システムを導入している場合、どのようなシステムでも「月の平均労働時間」を設定する必要がありますが、このメンテナンスを数年間していないという会社が非常に多いです。
月の平均労働時間が実態と乖離していたために、残業代の計算が間違っていたというケースも少なくありません。
でも毎年変えるのは面倒じゃない?
分かります。毎年月の平均労働時間が変わり、その度にシステムの設定を変更するのは面倒ですよね。
そこで月の平均労働時間を一定にするために、「毎年の労働日数を固定する」という会社もあります。
例えば年間の労働日を240日に固定するとした場合、1年間が365日なので休日数は125日です。
1年間の公休日を数えたところ、124日しかなかった場合は1日休日を増やす(例えばお盆休みや年末年始休みを増やす)という方法もあります。
この方法であれば、年間の労働日、労働時間、月の平均労働時間が一定に保たれるため、システムの設定を変更する必要はありません。
是非見直しを!
年末年始の忙しい中、ついつい見落としてしまいますが、とても大切なのが「年間の勤務カレンダー」です。
特に2024年はうるう年のため、2023年とは労働日数が異なる可能性が高くなります。
新しい年が始まる前に、是非見直しをお願いします。
お読みいただきありがとうございました。
ご相談・ご依頼はお気軽に社会保険労務士法人アーリークロスまでお願いいたします!